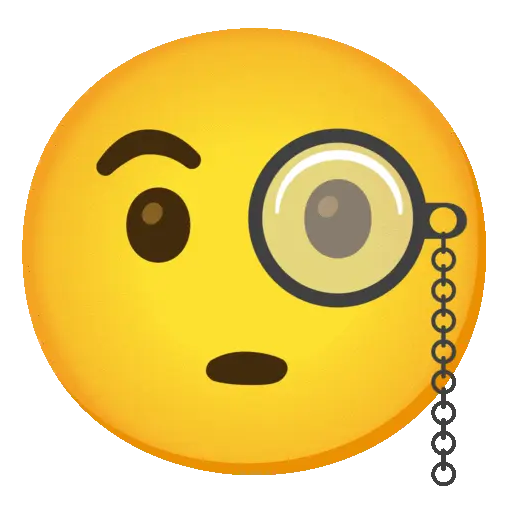<この記事は、【裏トーク】このチームで、死ぬまで一緒にブランドを見届ける。(中編)の続きです。>
後編では、「Chotto Time」の誕生秘話をお伺いしました。最終回となる今回は、プロジェクトを進めるなかで感じたrenらしさや「Chotto Time」のこれからについて聞いていきます。
一緒に夢中になってつくりあげる楽しさ
ープロジェクトを進めるなかで、renっぽいなと感じた部分はありますか
玉井)いい意味で、めんどくささがあることかな(笑)。
山田)“いい意味”とつけて、ごまかしてますね(笑)。
玉井)いや、本当に“いい意味”で言ってます!めんどくささと言ったものの、楽しさのほうが勝っていました。
木部)一緒にあれこれ考える機会が多かったですもんね。
玉井)そうですね。発注者と受注者みたいな関係性じゃなくて、ひとつのチームとして仕事している感覚がありました。僕からrenに対してインプットして、しばらく時間が経ったら、「チーン!アウトプットができました!」みたいなことじゃない。僕もアウトプットをつくるなかに一緒に混ざって、コネコネ考える。途中大変なこともあるけど、それも含めてチームだし。
山田)キャラクターを考える際も、すごく楽しそうでしたもんね。その様子を見て、僕らも楽しくなった。
玉井)本当に楽しい時間だったし、ストレスは全くありませんでした。このプロセスと後味はrenならではじゃないかな。大げさに言ったら、プロのチームに素人を入れる感じですし、もちろん嫌がる人もいると思います。「そっちの領域は任せます、こっちの領域は任せてください」みたいなスタイルもある。そんななかで、一緒に考えてつくりあげていくのがrenのスタイルなのかもしれない。
山田)「垣根をなくしてみんなでやる」というのは無意識のうちに実践していたのかもしれないです。「いい仕事は、いいチームから」と信じているから。

本当に伝えたいことを少し奥に置く
ー「一緒にやる」ということ以外に、renメンバーがプロジェクトを進めるうえで意識していたことはありますか
山田)株式会社りんねと、今回つくるブランドの関わりはずっと考えてましたね。
玉井)うちは「りんね」という会社だけど、「ひなのや」というブランドイメージのほうが強い。まわりから「ひなのやさん」と呼ばれることもあるし、株式会社ひなのやにしようかな、と考えたことがあるくらいです。
山田)そのくらい「ひなのや」というブランドのインパクトが強い。でも、構造を考えると、株式会社りんねがあって、そのなかに「ひなのや」と「Chotto Time」があるわけで。
りんねとのつながりを意識しつつ、「ひなのや」とも被らないブランドをどうつくるか。そこはずっと頭にありました。
玉井)「ひなのや」以外の主なブランドを開拓したいなと思っていたので、「Chotto Time」の誕生は嬉しいです。
山田)「ひなのや」はブランドとして確立されていて、販路にもすごくこだわっている。ブランドのあり方が、正装のようにカチッと決まっている。だから、急にダボダボの服を着よう!みたいな大胆な変化はしづらい。それに比べれば、今回つくった「Chotto Time」はもっとカジュアルなアプローチができる。「ひなのや」にはできないことができる。

玉井)表現のかたちは違っても、ブランドの基本のルーツや価値観は、株式会社りんねの考え方にあります。「ひなのや」をはじめた当時は、地方がどんどん衰退していったタイミングで、「なんとか再興させたい!」という思いがありました。それとは別に、「農の文化を大切にしていきたい」という思いもあった。でも現状は、「ひなのやさん=ポン菓子やさん」のイメージに留まってしまっている。そこを立て直したいなとも感じていますし、新しくつくった「Chotto Time」にも、「ひなのや」とは違った角度から、農の文化を取り入れていきたいと思っています。
山田)ですね。とはいえ、いきなり「農の文化が!」という話をしても、お客様には届かない。だから、「Chotto Time」のインターフェースはすごくカジュアルにしています。キャラクターを活かしながら、「かわいい!おいしい!」が入口。人間の本能的な部分です。そこから背景を深堀りしていくと、農の文化にたどり着く。「ただのお菓子じゃなくて、社会へのメッセージだったんだ」と気づいてもらう。ラーメンの汁を飲んだあとで器の底のメッセージに気づくような、押し付けがましくない仕掛けが大事だと思いました。
このチームで、死ぬまで一緒にブランドを見届ける
ー最後の質問になります。玉井さんにとってrenはどんな存在ですか?
玉井)会社レベルでいうと、まだ全貌がわかっていないのが正直なところ。やっている事業やSNAPでの取り組みを見ると、コミュニケーションをつくっている会社だと感じています。

玉井)関わってくれた山田さん、木部さんに対していうならチームです。仲間。このチームで、死ぬまで一緒にこのブランドを見届ける。歴史の証人のような感じかな(笑)。転職したり住む場所が変わったり、どうなったとしても、行く末を見届ける。僕らは見届けなきゃいけない。
木部)一緒に悩んで、一緒に喜ぶ。みんなで頭と手を動かしながらやってきましたし、それはこれからも変わりません。
山田)嬉しいとともに気が引き締まります。まだまだやれることがたくさんある。
玉井)いろいろやっていきましょう!僕は、自分たちにとっても社会にとっても、よりよい未来をつくるために仕事しています。「Chotto Time」もそう。「Chotto Time」が活躍すればするほど、人も社会もよくなるはず。現在の、都市にギューッと人とエネルギーが集まって、地方には誰もいないという構造はいびつに感じます。このままだと不幸せなことになってしまうという不安感だってある。そんな構造や不安をほぐすような存在に、「Chotto Time」がなれたらいいなと思います。
木部)二子玉川の催事では僕も店頭に立ったのですが、そのメッセージが届く瞬間があったように感じました。「Chotto Time」に込めた思いを伝えると、涙ぐむお客様もいらっしゃった。
玉井)僕らが取り組んでいることはきっと社会や未来のためになる。これからも一緒に試行錯誤していきたいです。
ーありがとうございました。
renは、つながりの課題にアプローチして、幸せな変化を起こすプロジェクトをデザインする会社です。トライ&エラーを通じて獲得してきた実践知をもとに、あなたとともに、信じられる答えを見つけていきます。少しでも話してみたいなと思った方は、ぜひ、お気軽にご相談ください。