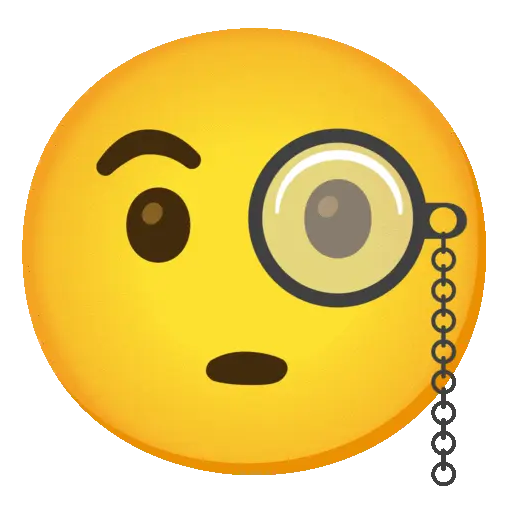こんにちは!広報部の松井です。この企画では、renと一緒に仕事をした方々の声を紹介しています。 今回登場するのは、「株式会社りんね」の代表を務める玉井さんです(以下敬称略)。renとともに新たに立ち上げたマイクロギフトブランド「Chotto Time」の企画から販売までのお話をお聞きしました。今回は、プロジェクトに携わったrenメンバーの山田、木部もインタビューに参加。全3編となるインタビュー記事です。ぜひ、ご一読ください。
はじめは飲み友達
ーrenとの出会いを教えてください。
玉井)最初の出会いは、愛媛県西条市です。メンマチョの山中さんの紹介でした。renというよりも、山田さんに出会ったというのが正しいかもしれません。
「Chotto Time」で仕事をするまでは、東京に来る際の飲み友達という感じだったかな(笑)。
山田)たしかに(笑)。一度、玉井さんが運営する「ひなのや」というブランドについて紐解こうと、セッションしたこともありましたね。
玉井)飲んでるだけじゃなかったですね(笑)。東京に来た際、たまたま時間が空いたタイミングでお邪魔したことがありました。もともと、renが運営するSNAPに行ってみたいとも思っていたので、その際、「ひなのやってなんのためにやっているの?」みたいな話をしました。

ー当時のrenはどんな印象でしたか?
玉井)まずは、メンマチョですかね。メンマチョのことはもともと知っていて、「すごいな」と思っていたんです。renが携わっていたことは、あとから知りました。
「すごいな」と思ったのは、商品を見た瞬間、心をキュッと持っていかれるところ。「なんだこれ!?」ってなるじゃないですか。お客さんにそうした感情を抱かせるのは簡単じゃないですから。
山田)ありがとうございます。「どうコミュニケーションを設計するか」を考えてつくったので、嬉しいです。
玉井)「どういうことだろう?」と聞いてみると、「放置竹林ってなかなか手ごわいぞ」みたいな話が出てくる。むっと真面目な顔で社会課題に取り組んでも面白くないから、キャッチーにやっていこうというのは、コミュニケーションとしてすごいなと思いました。

玉井)だから、「仕事を一緒にしてみたい」とはずっと思っていました。でも、なかなか叶わなくて。
山田)結果的に、飲み友達に落ち着いたわけです(笑)。
玉井)正直言うと、僕はあまり友達がいるほうではないんですよ。大人数で飲んだりもしない。苦手なの。でも、山田さんとは話が合うから、ずっと話していられる。仕事の話でワイワイ盛り上がる飲み会って楽しいじゃないですか。
だからこそ、「飲んでいるだけではもったいない!なんか一緒に仕事やりたいぞ!」って思っていました。

ーおふたりの関係性が垣間見えて微笑ましいです。こうした経緯が、今回の仕事につながったわけですね。
玉井)そうですね。はだか麦を使った麦チョコの開発や製品ブランディングを進めている段階で、「これなら一緒に仕事ができる!」とrenに依頼しました。
山田)声を掛けてもらって、純粋に嬉しかったです。
現地視察で見えてきた苦悩と“ならでは”の切り口
ーブランド開発はどのように?
玉井)はだか麦の産地を見てもらおうと、まずは愛媛に来てもらいました。早朝散歩してたら鹿やイノシシに会うような、田舎の耕作放棄地の棚田に来てもらいました。

山田)地域の人たちに混じりながらおにぎりを食べたり、味噌汁を飲んだり。はだか麦を使ったどんな商品があるのか、市場調査にも行きましたね。
玉井)車に乗って愛媛県内のはだか麦を扱った商品を見て回りたかったんです。いろんな現状を知ってほしくて。でも、全然売ってなかった。
山田)「全然売ってないじゃないか!」と玉井さんが怒りを感じて、役所に電話したら「販売やめちゃいました…」と報告されたこともあった(笑)。
玉井)愛媛県の松前町は、地元のニュースになるくらい、はだか麦の商品化に熱心な町なんですけど、売り場をまわっても売ってなかった。「ニュースで見たのにないんですけど!」と電話しちゃいました(笑)。もやもやっとした気持ちがあったのかな。
山田)一連の現象を面白いと思いました。つまり、いろんなところが商品化にチャレンジしているが、ヒットせずに終わってしまうということ。グルテンが含まれていないはだか麦自体が、お菓子に向いていない性質とも知って、難しいけどチャレンジしがいのある仕事だと思いました。
ーひと筋縄ではいかなそうな道のりですね。
玉井)はだか麦は、素材として強いわけではありません。市場調査をしたり、産業研究センターにも行って研究員の人とも話したりしたけど、長所がなかなか見つからない。栄養価が高いといっても、もち麦には劣る。
山田)愛媛に行って色々見てまわったけど収穫が少なく、わりと落ち込みました。そこで、ひとまず、はだか麦にとらわれずに考えようと切り口を変えました。そこで見えてきたキーワードは、「ひなのや」の由来です。
玉井)田舎の美しさとか田舎のいいところをお届けしていくのが「ひなのや」なんです。「観光」の語源を辿ると、「光」という字には、その土地自体の魅力や、その土地にあるいいものという意味があるそうです。「ひなのや」には、土地の光を掘り、育て、届けていく、という思いがあります。

山田)田舎の美しさというと、なにも風景や生産物だけじゃない。愛媛で過ごしたなかで、印象深かったのは”休憩の時間”でした。玉井さんにとっては日常かもしれないけど、僕にとっては幸せな時間だった。
玉井)畑にテーブルとベンチを置いて、お昼ごはんを食べた。その場に自治会の三役のおじさんたちも来てくれた。彼らがベンチに腰掛けた途端、ベンチがひっくり返っちゃったりなんかして(笑)。本当にもうドリフみたいで笑っちゃいましたね。
山田)はだか麦の機能性じゃなくて、こういう“休憩の時間”に注目するのがいいんじゃないのかなって思いました。そこで玉井さんに、「ちょっとそろそろ休憩しよ?を地元の言葉で言ってくれませんか?」と聞いてみたんですよ。
玉井)「ちょっとぼちぼちぼち休憩せん?」って。
山田)「それだ!」と思いました。その夜、ホテルのホワイトボードをかりて、色々考えて、新ブランドの大きな方向性が固まりました。
玉井)うちのお菓子を食べると、ちょっと気持ちが楽になったり、グッて張っている気持ちが緩んだり。美味しいとか、栄養だけじゃないメッセージを発信できるブランドにできたらいいなと気づきました。
<記事の内容は中編に続きます>